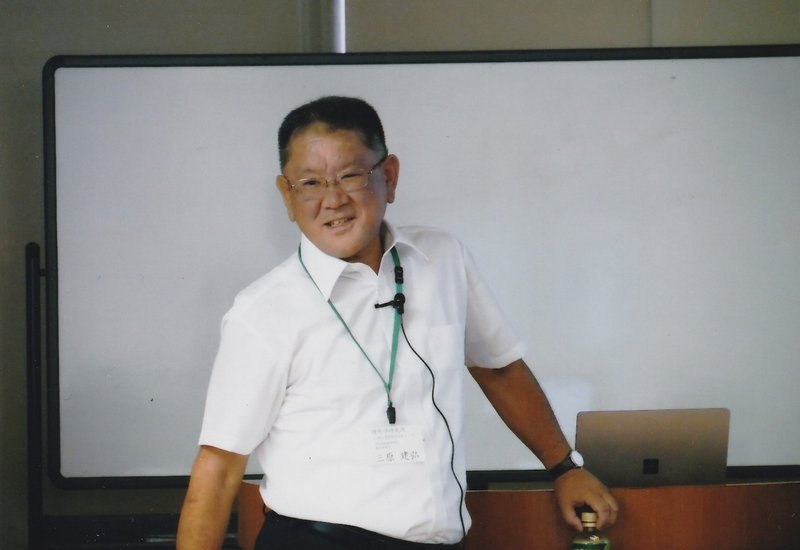演題:スーパーコンピュータで迫る物質創成の謎

講師 : 青木 保道(あおき やすみち)先生
国立研究開発法人 理化学研究所
計算科学研究センター 連続系場の理論研究チーム チームリーダー
講演概要
世界を構成する物質の質量は、素粒子の複雑な相互作用によって生み出されます。その中でも最も重要な相互作用が量子色力学(QCD)という理論で説明できます。QCDから物質の質量を導くには、その複雑な相互作用をスーパーコンピュータでシミュレーションするのが最も有力な手法です。1980年にアメリカで最初のシミュレーションが行われて以来、手法の改良とコンピュータの性能向上により、今では初期宇宙の物質創成時のシミュレーションができるようになってきました。本講演ではスーパーコンピュータ「富岳」で行われているそのような計算の最前線に触れつつ、仁科先生が日本に切り拓いた素粒子物理の現在と未来を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。
講演の様子
初めに講演の結論、スーパーコンピュータ(スパコン)でのシミュレーションによるQCD相転移の計算結果が示されました。陽子や中性子が溶けるほどの高温で何が起きるかを表し、ビッグバン直後で高温だった初期宇宙での物質創成に関係しているそうです。
まずスパコンのシミュレーションではどのような計算をしているのかを、円周率の計算を例に説明されました。
あらゆる物質は原子でできていて、原子の中心には陽子と中性子が集まった原子核があります。陽子はクォーク3個からなり、クォークの質量は陽子の質量の300分の1であり、一見不思議ですがQCDという理論を用いたスパコンによるシミュレーションで導けます。
相転移について、水は0℃で氷になり、100℃で水蒸気になる、つまり温度で相が転移すると説明がありました。陽子や中性子が高温で溶ける時の相転移をスパコンで計算したのが冒頭の図で、「場の移行はあるが非連続な相転移はない」という結論が得られたそうです。
実験結果と併せて物質創成の謎に深くメスを入れる事を目指しアルゴリズム開発中との事で、今後の研究の進展が楽しみです。