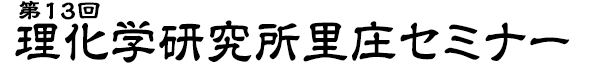

| 第13回理化学研究所里庄セミナー開催 平成16年8月21日(土) 仁科会館にて |
|
| 第一線で研究に取り組まれている研究者のお二人から、ゲノム解明の意義からこれからの課題に至るまでを網羅して頂き、高校生から高齢者まで、主婦から大学の研究者に至るという幅広い聴衆の、様々な好奇心にお応え頂きたました。 豊富な映像の他に、ゲノムのサンプルやゲノムブックの実物の回覧があり、またベースになる水溶性の紙をビーカーの水で溶かしたりと、多様な展開に魅了され、時の経つのを忘れた2時間半でした。また、高校生から医師にいたる、またご子息が理研で働いている高齢者からと多様な質問にもお応え頂き和気あいあいの内に終了いたしました。 |
|
 |
河合 純 先生 独立行政法人理化学研究所 横浜研究所 ゲノム科学総合研究センター 遺伝子構造・機能研究グループ 遺伝子情報解析研究チーム チームリーダー |
| 演題:全部の遺伝子が一冊の本になる −遺伝子百科事典プロジェクトからDNAブックへ−
生物が遺伝子の言葉で語られる時代になってきました。大規模な解析により明らかにされた遺伝子の情報は、病気の治療、薬の開発をはじめ、作物や家畜の品質改良など様々な分野で重要なものとなっています。私たちは病気の診断や治療を最終的な目標と考え、「遺伝子百科事典プロジェクト」を進め、マウス(ハツカネズミ)の持つ遺伝子の解析を行ってきました。ヒトの病気は全てマウスでも観察されるからです。マウスを理解することはヒトを理解するための近道なのです。「遺伝子百科事典プロジェクト」によりマウスの遺伝子の全体像がわかりつつあります。またマウスの全部の遺伝子を集めた本(DNAブック)も見せて頂きました。 |
|
| 竹田 忠行 先生 独立行政法人理化学研究所 横浜研究所 ゲノム科学総合研究センター ゲノム構造情報研究グループ ゲノム機能解析研究チーム 上級研究員 |
 |
| 演題:ゲノム解明の意義と方法および現状
ゲノムとは生物が生命活動を維持するために必要な一組の染色体で、その本体は4種類の塩基が並んだデオキシリボ核酸(DNA)という物質から作られています。ゲノムは生命の設計図であると同時に、生物固有の遺伝情報として子孫に受け継がれます。ゲノムには生命の本質を決定するために多くの遺伝子が存在し、個々の遺伝子の役割を理解することが生命科学の中心課題となっています。 |
|