|
ロボットコンテストに向けた
「ロボット製作講習会」を開催しました |
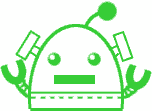 |
|
ロボットコンテストに向けた
「ロボット製作講習会」を開催しました |
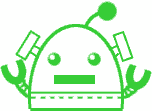 |
|
日時:令和2年2月15日(土)13:30〜16:30 場所:仁科会館2階 仁科記念ホール 講師:小野 博俊 先生(高梁城南高等学校) |
|
1. はじめに科学振興仁科財団では、岡山県内の中学生・高校生に参加を募り、毎年夏に里庄中学校体育館でロボットコンテスト(ロボコン)を開催しています。 この度、ロボコンに参加してみたいけれどロボットの作り方が良く分からないという声に応え、「ロボット製作講習会」を開催しました。仁科会館の職員2名も参加して1台製作しました。右の写真は仁科会館の職員が製作したロボットです。実物をご覧になりたい人や操作してみたい人は仁科会館で職員にお声がけください。 2. 製作したロボット今回の講習会では当財団主催のロボコンに出場できるサイズのロボットの足回りを製作しました。当財団主催のロボコンではロボットのサイズの制限は毎年変わらず縦70cm×横50cm×高さ150cm以内なので、足回りは毎年使用することができます。ただし、ロボコンのルールは毎年変わるため、アイテムを運ぶ部分は毎年新しく考えて製作する必要があります。 このロボットは1辺40cmの正方形の木の板(厚さ5.5mmのMDFボード)に動力車輪2輪とキャスター2輪を取り付けていて、コントローラーで操作することができます。動力車輪はRCカー(ラジコンカー)用のタイヤをギヤボックス(モーターとギアとシャフトのセット)で動かします。 電源はコントローラーには内蔵せず、コントローラーから電気コードを引き出してロボットに貼り付けた電池ボックスにつないで供給しています。ロボコン中学校部門では外部電源の使用が認められていますので、ロボコン大会では電気コードは外部電源につなぎます。電源をコントローラーではなく外部に置くことによりコントローラーの電池ボックス部分が空になりますので、そこに新たなスイッチを増設することができます。 |
3. 準備3-1. 部品製作に必要な部品の一覧表です。4,000円から5,000円で調達できます。 |
| 材料 | 詳細 | 入手方法 | 備考 | |
| (1) | コントローラー | タミヤ 楽しい工作シリーズ No.106 4チャンネルリモコンボックス |
ネット通販または模型店 | 本来は自作が望ましいが、今回は市販品を購入した |
| (2) | タイヤ 2輪 | グリッドグレインタイヤ RC1:10 タイヤ外径65mm |
ネット通販または模型店 | |
| (3) | キャスター 2輪 | 自在車 タイヤ径38mm |
ホームセンター | |
| (4) | ギヤボックス 2個 | タミヤ テクニクラフトシリーズ No.7 4速パワーギヤボックスHE | ネット通販または模型店 | |
| (5) | MDFボード | 大きさ:400mm × 400mm 厚さ:5.5mm |
ホームセンター | ホームセンターで切ってもらう |
| (6) | 電池ボックス | 単3乾電池3本用 | ネット通販またはホームセンター | |
| (7) | M3なべ小ねじ | 長さ40〜50mm(4本)、25mm(4本)、15mm(8本) | ホームセンター | |
| (8) | M3ナット、ワッシャー | ナット16個、ワッシャー24個 | ホームセンター | なべ小ねじに付属していた |
| (9) | 電気コード | 2芯コード(0.3mm2以上)1m 2色のコードが分かり易くて良い |
ホームセンター | 3mあると便利 (4.5節参照) |
| (10) | ハンダ | ホームセンター | ||
| (11) | ビニールテープ | ホームセンター | ||
| (12) | 両面テープ | ホームセンター | ||
| (13) | 電池 | 単3アルカリ乾電池3本 | ホームセンター |
3-2. 工具製作には以下の工具が必要です。 |
|
4. 製作4-1. ギヤボックスの組み立てギヤボックスとはモーターの回転をギアを使ってシャフトに伝える部品です。説明書にしたがって組み立てます。いきなり組み立てるのではなく、まず説明図をよく読んで内容を理解しましょう。 さらっと書きましたが、工作に慣れていないとこの工程が結構手間取ります。今回のロボット製作ではここが一番大変なので、工作が苦手な仁科会館職員もがんばって乗り越えました。 シャフトの位置を2種類から選べますが、今回は説明図の「A」を選びました。ギア比を4種類から選べますが、今回はスピード重視で39.6:1にしました。パワー重視にしたい場合はギア比を大きくします。 組み立てが終わったら、シャフトを回転させてギアがきちんと噛み合っていることを確認します。無事に動いたら完成です。噛み合っていない場合は分解して調整します。 |
組み立てたギヤボックス。写真はボードに取り付けた後の状態 (写真をクリックすると拡大) |
4-2. コントローラーの組み立て説明書にしたがって組み立てます。ただし、外部から電源を供給するためにコントローラーの裏にドリルで穴をあけて2芯コードを取り付けます。 こうすると単一電池をコントローラーにつける必要がなくなりますので、コントローラーの電池ボックス部分(下半分)が空間になります。その空間にロボットを動かすためのスイッチを増設することができます。径6.5mmの穴を開けて、最大5個のスイッチが増設可能です。今回の講習会では、スイッチの増設はしませんでした。 |
組み立てたコントローラー (クリックすると拡大) |
コントローラーに穴を開けてコードを取り付ける (クリックすると拡大) |
4-3. ボードに穴開け穴あけドリルを使って、MDFボードに部品を取り付ける穴を開けます。ギヤボックス、キャスター、電気コードの引き出し穴を3mmで開けます。穴を開ける場所はこのレポートの最初に掲載した完成品の写真を参照してください。 右の写真はギヤボックスを取り付ける穴を開けている様子です。今回は小野先生が穴を開けるための治具を用意してくれました。この治具をダブルクリップでボードに固定して、ドリルで穴を開けていきます。コツとしては穴を開けるごとにネジを入れていくと、穴の位置がずれません。 穴開け用の治具がない場合は、ボードにギヤボックスやキャスターをつける位置を実際に部品を載せて確認して、その状態で鉛筆でボードに穴の位置を書いてから、位置がずれないように穴を開けます。 |
ドリルでボードに穴を開けている。 治具を使って穴の位置を決めている。 (写真をクリックすると拡大) ギヤボックス用の穴と穴開け治具 (写真をクリックすると拡大) |
4-4. 各部品の取り付けと電源コードの仮止めまず、ねじとナットとワッシャーを使って、ギヤボックスとキャスターをボードに取り付けます。ギヤボックスには40〜50mmと25mmのネジを、キャスターには15mmのネジを使います。 次に、ギヤボックスのシャフトにタイヤを取り付けます。ギヤボックスのシャフトの穴に短いシャフトを取り付け、六角形の部品に短いシャフトを取り付けます。そしてその六角形の部品をタイヤにはめて、ナットとワッシャーでしっかり固定します。文章で説明するとややこしいのですが、右の写真を見てもらうと仕組みがすぐ分かると思います。 電池ボックスは両面テープを使ってロボットの表側に固定します。取り付ける場所はこのレポートの最初に掲載した完成品の写真を参照してください。キャスターよりもタイヤに荷重をかけたいのでタイヤ寄りに電池ボックスを貼り付けています。 最後に電気コードをつないでいきます。つなぐときは、まず仮止めして動作を確認して、動作確認が終わってから本止めします。仮止めはコードの電線部分同士を撚ってつなぐだけで構いません。 初めに、乾電池は入れずに電池ボックスのコードをコントローラに穴を開けて接続した2芯の電気コードにつなぎます。次に、コントローラーのコードをギヤボックスに接続します。左側のスティックの4芯コードのうち赤と白を左のギヤボックスに、右側のスティックの4芯コードのうち赤と白を右のギヤボックスに接続します。どう接続すれば正しい方向に動くかは、つないで動かしてみないと分かりませんので、まずは適当に接続します。 |
4-5. 動作確認と調整部品の取り付けと電気コードの仮止めが終わったら、電池ボックスに乾電池を入れて動作確認します。タイヤが動かない場合は、コードの配線が外れていないか、ギヤボックスのギヤが外れていないかなどを確かめましょう。タイヤが動いたらロボットを操作してみて、コントローラーの上下とタイヤの前進後退が対応するように電気コードのつなぎかたを試行錯誤する必要があります。 正しく動作することが確認できたら、電気コードを本止めします。本止めはハンダ付けしてビニールテープで巻きます。ただし、コントローラーのコードが短いため、このままだと中腰でロボットを操作しなければなりません。ですので、電気コードを間に1m以上はさんで延長するとロボットの操作が楽にできます。 |
5. 終わりに当財団主催のロボコンに参加できるロボットの足回りが完成しました。この足回り上にアイテムを運ぶ機構を設計・製作していきます。アイテムの運搬機構はロボコンのルールに合わせて製作する必要があります。ルールを作る審査委員の先生がたの予想を超える独創的な仕組みをぜひ考えてください!ロボコンへの参加をお待ちしています。 |